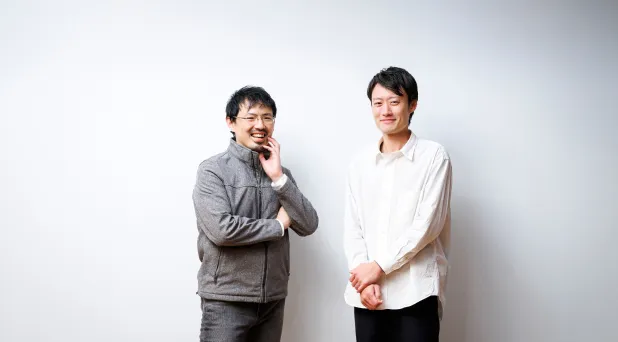- 澤村:
- 初代・2代目の時代は、地元の祭りに参加したり、商工会の仲間と一緒に商店街を使ったまちおこしをしていました。私が代表になってからは、地域のメンバーを巻き込んで、地元工芸家のアトリエを巡るイベントをやったり、高島市に対して各地域の活性化案を提言していましたが、地域に還元できているという手応えが無かったんです。そんな中で、手応えを感じ始めたのが自社で運営する「SAWAMURAマルシェ」。来場者が「ゆたかな暮らし」を考える場にする、をコンセプトに毎回アプローチを変えて企画しています。マルシェなど手段や枠組みを活かし、多様な視点からアプローチすることで、最終ゴールに近づくかもしれない、と考えるきっかけをもらいましたね。
- 南:
- そうですね。私がマルシェの委員長になった時は、数あるマルシェの中で「建築の会社がやる」というアイデンティティを、自分なりに考えていました。空き家利活用を促したいという会社の意向もあったので、すぐに直結せずとも、SAWAMURAのことや暮らし方を考えるヒントになりそうなワークショップの企画を提案して、少しずつ発展させてきました。